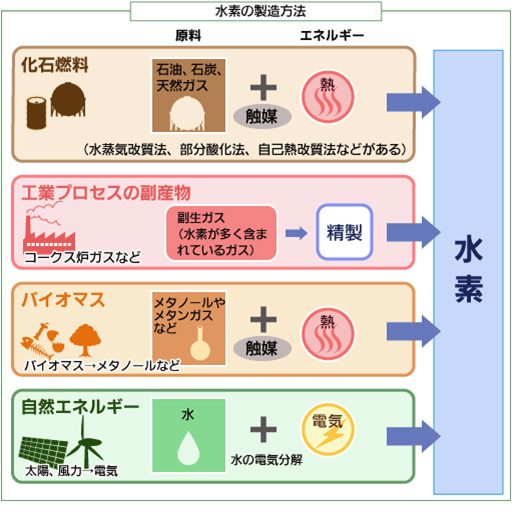SMHTAについて
趣旨
水素はエネルギーの分野で注目を集めているが、同時に、その生体に対する優れた効果は
医療分野のみならず、農業、畜産、水産など多方面に変革をおこし、我々の生活全般を
大きく変える可能性を秘めている。ここに注目して、NPO法人新共創産業技術支援機構(ITAC)では
新たな産業創出を目指す『水素分子応用技術研究会(The Society of Molecular Hydrogen
Technology and applications (SMHTA)』をスタートする。ここでは、水素分子の応用に関して
幅広くその可能性を探り、新たな日本の“ものづくり”の一助とする事を目的とするが、先ずは、
農業分野、その中でも植物の生育や保存に焦点を当て、大学や研究機関との連携を基に可能性を追求する。
↑ページのトップへ
組織
名称
水素分子応用技術研究会
研究会役員
代表 : 永田 鎮也 日本光電工業株式会社 荻野記念研究所 主席研究員 薬学博士
副代表: 楽木 宏実 大阪大学大学院教授 医学系研究科内科学講座 老年・腎臓内科学
副代表: 楽木 宏実 大阪大学大学院教授 医学系研究科内科学講座 老年・腎臓内科学
幹事
和田 光生 大阪府立大学大学院生命環境科学研究科資源植物機能学講師
岩瀬 哲雄 NPO法人ITAC理事・事務局長
岩瀬 哲雄 NPO法人ITAC理事・事務局長
アドバイザー(五十音順)
天尾 豊 大阪市立大学教授、人工光合成研究センター所長
梅野 正義 シーズテクノ株式会社 取締役研究開発部長、中部大学 総合学術研究院 客員教授
大河内正一 法政大学生命科学部 教授
大野 欽司 名古屋大学大学院医学系研究科 神経遺伝情報 教授
重岡 成 近畿大学農学部長 バイオサイエンス学科教授
清水 浩 京都大学大学院農学研究科地域環境科学専攻農業システム工学教授
白川 功 NPO法人ITAC理事長、日本データセンター理事長、大阪大学名誉教授
多田 安臣 名古屋大学大学院理学研究科 教授
南後 守 大阪市立大学 複合先端研究機構 特任教授
福田 弘和 大阪府立大学 工学研究科 准教授
松本 紘 国立研究開発法人理化学研究所理事長、京都大学名誉教授、
(公財)国際高等研究所長、元京都大学総長、前NPO法人ITAC理事長、ITAC顧問
吉田 朋子 大阪市立大学教授、人工光合成研究センター副所長
和田 光生 大阪府立大学大学院生命環境科学研究科資源植物機能学講師
梅野 正義 シーズテクノ株式会社 取締役研究開発部長、中部大学 総合学術研究院 客員教授
大河内正一 法政大学生命科学部 教授
大野 欽司 名古屋大学大学院医学系研究科 神経遺伝情報 教授
重岡 成 近畿大学農学部長 バイオサイエンス学科教授
清水 浩 京都大学大学院農学研究科地域環境科学専攻農業システム工学教授
白川 功 NPO法人ITAC理事長、日本データセンター理事長、大阪大学名誉教授
多田 安臣 名古屋大学大学院理学研究科 教授
南後 守 大阪市立大学 複合先端研究機構 特任教授
福田 弘和 大阪府立大学 工学研究科 准教授
松本 紘 国立研究開発法人理化学研究所理事長、京都大学名誉教授、
(公財)国際高等研究所長、元京都大学総長、前NPO法人ITAC理事長、ITAC顧問
吉田 朋子 大阪市立大学教授、人工光合成研究センター副所長
和田 光生 大阪府立大学大学院生命環境科学研究科資源植物機能学講師
事務局
岩瀬 哲雄 NPO法人ITAC専務理事
住所
〒530-0037大阪市北区松ヶ枝町6番3号 篠原松ヶ枝ビル302号室
NPO法人新共創産業技術支援機構(ITAC)内
NPO法人新共創産業技術支援機構(ITAC)内
電話/FAX
TEL/FAX: 06-6556-6018
携帯電話: 090-9982-6760
携帯電話: 090-9982-6760
e-mail
↑ページのトップへ
本研究の背景:水素分子応用技術研究会
水素は次世代エネルギーとして期待を集めているが、生体に対する効果についても研究が進められており
医療分野への応用に期待が寄せられている。医学分野への応用の道を開いたのは、2007年のNature
Medicine 掲載された大澤等の論文である。ここでは、水素分子が細胞中のヒドロキシルラジカル(·OH)や
ヘペルオキシナイトライト(ONOO−)など、強い酸化力をもった活性酸素種、活性窒素種を消去することが
示された。Ohsawa et.al.; Nat. Med., 13, 688‒694(2007).
それ以来、主にモデル動物を用いた実験が進められ、水素の治療効果や予防効果についての多数の論文が 発表されており、これらの論文では、ほぼ全ての臓器で直接的あるいは間接的に酸化ストレスが関与する 疾患モデルに対して水素の効果があることが示された。
一方、水素分子の植物への影響についての研究は、南京農業大学のYanjie Xie等のシロイヌナズナの 乾燥耐性に対する水素の効果についての論文が注目を集め、その後研究が始められた。 Yanjie Xie,et al., “Hydrogen, Stomatal Closure, and Drought Tolerance”, Plant Physiol. Vol. 165, 2014
当研究会では、上記の背景をもとに、水素分子の植物への効果について幅広く探索すべく、 大学等の研究機関との連携を中心として研究開発を進める。
それ以来、主にモデル動物を用いた実験が進められ、水素の治療効果や予防効果についての多数の論文が 発表されており、これらの論文では、ほぼ全ての臓器で直接的あるいは間接的に酸化ストレスが関与する 疾患モデルに対して水素の効果があることが示された。
一方、水素分子の植物への影響についての研究は、南京農業大学のYanjie Xie等のシロイヌナズナの 乾燥耐性に対する水素の効果についての論文が注目を集め、その後研究が始められた。 Yanjie Xie,et al., “Hydrogen, Stomatal Closure, and Drought Tolerance”, Plant Physiol. Vol. 165, 2014
当研究会では、上記の背景をもとに、水素分子の植物への効果について幅広く探索すべく、 大学等の研究機関との連携を中心として研究開発を進める。
↑ページのトップへ
研究目的
水素分子は将来のエネルギー源として期待を集めているが、一方で医学分野を中心として
生体に対する特有の効果が注目を集めている。当研究会では医学のみならず、健康、農業、
畜産、水産等の幅広い応用分野に対し新たな産業創生・振興に取り組んでいく。
↑ページのトップへ
実施計画
水素分子の研究開発を効率的に推進するため、プロジェクト志向の産学官連携体制の構築を目指す。
具体的には、先ず水素分子の植物への応用について取り組む。この研究分野はまだ未知の領域であり、
有効性のメカニズムも確立していない。当研究会では、
・第1段階では産学連携の研究プロジェクトを発足させ、科研費、関連する民間や公的な助成金等を得
ながら基礎的な研究を推進する。
・第2段階として幅広く研究メンバー、企業を結集し、農業全般への適用を更に発展させていく。
・第3段階として水素分子の応用範囲の拡大を目指し、医療・健康・農業・畜産・水産等の分野の研究
推進と参加企業の共創による事業創生を目指す。
・第1段階では産学連携の研究プロジェクトを発足させ、科研費、関連する民間や公的な助成金等を得
ながら基礎的な研究を推進する。
・第2段階として幅広く研究メンバー、企業を結集し、農業全般への適用を更に発展させていく。
・第3段階として水素分子の応用範囲の拡大を目指し、医療・健康・農業・畜産・水産等の分野の研究
推進と参加企業の共創による事業創生を目指す。
↑ページのトップへ
活動内容
本会は、前条の目的を達成するために、次の各号の活動及び支援を行う。
(1) 水素分子の生体に対する影響、効果の評価とそのメカニズムの解明についての研究開発
(2) 水素分子の効果、メカニズムに関係した論文の投稿
(3) 水素分子応用に関する知的財産権の創出
(4) 研究推進に要する各種助成金等の獲得
(5) 定期的な研究会・講習会等の開催
(6) 水素分子技術に関する技術動向・市場動向の調査・分析
(7) 本活動に関連する情報の発信・PR広報
(8) その他、本会の設立趣旨を達成するために必要な活動
◎研究会:3~5回/年 開催予定
(1) 水素分子の生体に対する影響、効果の評価とそのメカニズムの解明についての研究開発
(2) 水素分子の効果、メカニズムに関係した論文の投稿
(3) 水素分子応用に関する知的財産権の創出
(4) 研究推進に要する各種助成金等の獲得
(5) 定期的な研究会・講習会等の開催
(6) 水素分子技術に関する技術動向・市場動向の調査・分析
(7) 本活動に関連する情報の発信・PR広報
(8) その他、本会の設立趣旨を達成するために必要な活動
◎研究会:3~5回/年 開催予定
↑ページのトップへ
ご参考
↑ページのトップへ